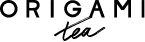ーーParklet
自然をフィールドにしてきたからこその、土地の個性を活かす場所づくり
――ここからはMaxに話を聞いていきます。ここで表現したことについて、ご自身のバックグラウンドも含めてお話を聞けたらと思います。まずはクリエイティブディレクターとしてのご経験について教えていただきたいのですが、出身地のカリフォルニアから日本へ来ることになった経緯から伺えますか?
Max:僕はこれまで自然の中で過ごす経験を多く重ねてきました。その経験や、日本へ来るようになったことが、『TERASU』や今のさまざまな仕事につながっています。
10代の頃はスノーボードやマウンテンバイクに取り憑かれ、山の中を走り回っていました。マウンテンバイクのプロとして活動していた時期もあります。ですが義務感でトレーニングをすることにうんざりしてしまい、大きな怪我をしたこともあって、カリフォルニアの大学へ進学しました。そこではメディアスタディーズを学び、映像などを本格的に勉強しました。必修科目の語学で日本語を選択したことが、日本と行き来するようになったきっかけです。日本へは13歳の時にスノーボードをしに来たことがありました。北海道の雪は最高でしたし食文化や暮らしも興味深く感じたことが印象に残っています。


Max:語学もクリエイティブも、仕事をした方が実体験として学べると思いました。9年前に日本で働き始めて以来、学生の頃から二拠点で働いていましたが、コロナ禍がやってきて、行き来ができなくなって。Terrainの立ち上げのタイミングでこちらに留まることにしました。
『TERASU』は山、海、食文化を軸に、調理器具の製作や自社出版などを行うクリエイティブスタジオ。学生のころ真夜中に起きて急に思いついたプロジェクトです。あらゆる生に着目し、新しい物事の捉え方を照らし出すことを目的としています。スノーボーダーの写真家を始め、尊敬する面々に話したところ、絶対やるべき、サポートするよと背中を押してもらって。いろいろなフィールドの職人、アーティスト、シェフと共に、彼らが活動することにより得た経験をもとに出版物や調理器具を形にしています。


Max:英語で「Parklet」は「公園ちゃん」とでも言うようなニュアンス。公園の延長線上にある、自然を感じられる、小さな公園とでも言えるような場所をイメージしました。
カリフォルニアでも日本でも、親しくなる作家やクリエイターは、自然そのものを表現したり、素材をそのまま生かして使う人が多くいました。ベイカーの友人についても、パンを焼く行為そのものが同様の表現に思えました。Parkletの切り株をそのまま活用したベンチテーブルや、サワードゥブレッドをはじめとしたものの仕上がりや味わいは、そうした表現に基づいています。
――カリフォルニアと日本の自然と文化。そしてこの東日本橋の街の文化が、この場で融合していくのが楽しみです。場所作りにおいてこだわった点は?
Max:美味しいパンとコーヒーがあるところには必ず人が集まり、コミュニティが生まれていく。他の所より美味しいとか、おしゃれでこだわりのあるパンとコーヒーとかというより、新しい一貫性のあるコミュニティを生み出していくためには自分達で作らなければならないと考えました。

Max:西海岸、特にサンフランシスコでは、コミュニティの色や町の文化は、いいベーカリーのようなところで、アーティストの表現を通じて知ることができます。例えば、友人であるアーティストのIdo Yoshimotoは、巨大な木を半分に切ってSolange Roberdeauというアーティストと一緒に染めてタルティーンベーカリーの外観に飾りましたが、それがずっと街の風景となっています。岡本太郎も言っていましたが、ある場所の文化を知りたいならば、ローカルたちが通う飲食店にいくのが一番だと。僕はベーカリーに関しては本当にその通りだと思っています。つまり、いいコーヒーがあるところでは街の魅力を見ることができる。

Max:Terrainでは、今後も柔軟性を持っていきたいです。クライアントワークもやるかもしれないし、このままだとただの飲食グループに見えるかもしれませんが、メディアや紙媒体など色々やっていきたいです。
個人的には、今やりたいことは二つで、一つは公園を作るようなこと。Parkletにも共通する要素がありますが、もっと外の地形を活かして作り込んでいくようなことを。もう一つは、美術館関連の何かを。展示のキュレーションか、形は色々あると思いますが。


自然を感じたい、自然と共にありたいという欲求は誰しもが抱くもので、さらにそれを日々の暮らしに落とし込んでいく作業は時に難しいものだが、Terrainチームはそれを都市と自然という文脈の中で実践していた。そこには彼らがこれまで自然と向き合いながら手がけてきたクリエイティブの積み重ねがある。
彼らはあらゆる自然環境や地域に触れてきたことで、それぞれの土地の風土や、個人、コミュニティの在り方に対して寛容で、それらを尊重し、生かしていた。
状況を観察し、次々に巡り合わせを生かしていく彼らの仕事の仕方や生き方そのものが、まるでスノーボディングしているかのように感じられた。